| 日時 | 2007年12月13日(木)13:30~17:05 |
| 会場 | 発明会館ホール 発明会館B2 (〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14) |
| 主催 | COBOLコンソーシアム/日経BPセミナー事業センター |
| 協賛 | 富士通/富士通ミドルウェア、日立製作所、 東京システムハウス、NEC、他 |

企業の基幹業務システムに採用され、その膨大な資産によって現在のIT社会の根幹を支えるCOBOLの実力に改めて着目しました。第14回目となる今回のセミナーでは、「基幹システムの‘いま’と‘これから’を支え続けるCOBOLの力」というテーマで、COBOLの活用に成功している企業の事例をご紹介いたしました。
セミナーは、「情報システム開発・保守、見える化への挑戦~ユーザー側から見たソフトウェアメトリックス」というテーマで、社団法人日本情報システム・ユーザー協会専務理事 細川泰秀氏の基調講演で始まりました。
続く、事例紹介のセションでは、「COBOL資産を活用したコカ・コーラセントラルジャパンにおける新営業システム構築事例」と題し、コカ・コーラセントラルジャパン情報システム部部長補佐 千代田紀行氏、「Linux環境でのCOBOLマイグレーション」と題し、エステーITグループ/マネジメントスタッフ 照井琢磨氏、「COBOL・MIDMOSTIによる銀行オープン基幹系システム構築事例-S-BITS・BankVision-」と題し、日本ユニシスSW&サービス本部S-BITS共同OSC 基盤プロジェクト長 馬場定行氏、「T社様メインフレームからの移行事例」と題し、NECソフト PFシステム事業部プロフェッショナルサポートグループプロジェクトマネージャ 宇治郷二郎氏から、それぞれご講演いただきました。また、「これからもCOBOL」という内容も含め、COBOLコンソーシアムの新会長に就任した高木渉からクロージングのご挨拶をさせていただきました。
セミナー詳細については,日経BP社各誌で紹介されます。ご参加いただけなかった皆様には各誌で当日の様子をご覧いただけると思います。
師走のお忙しい時期のセミナー開催でしたが、当日は182名というの方々にご参加いただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。
COBOLコンソーシアムの活動は、皆様からのご支援をいただきながら、2007年12月11日で満7年を迎えることができました。先日の幹事会では、「今後も活動を継続する」という議案が決議されました。COBOLコンソーシアムは新会長の下、今後も皆様に有益な情報を公開して行く所存ですので、引き続きご支援の程お願い申し上げます。
| プログラム |
 | ●基調講演 情報システム開発・保守、 見える化への挑戦 ~ユーザー側から見たソフトウェアメトリックス 社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 専務理事 細川 泰秀 氏 発表資料(PDF:598キロバイト) |
 | ●事例講演 COBOL資産を活用したコカ・コーラ セントラルジャパンにおける 新営業システム構築事例 コカ・コーラ セントラル ジャパン 情報システム部 部長補佐 千代田 紀行 氏 発表資料(PDF:715キロバイト) |
 | ●事例講演 Linux 環境でのCOBOL マイグレーション エステー ITグループ / マネジメントスタッフ 照井 琢磨 氏 発表資料(PDF:202キロバイト) |
 | ●事例講演 COBOL・MIDMOSTによる 銀行オープン基幹系システム構築事例 -S-BITS・BankVision- 日本ユニシス SW&サービス本部S-BITS共同OSC 基盤プロジェクト長 馬場 定行 氏 発表資料(PDF:1,122キロバイト) |
 | ●事例講演 T社様 メインフレームからの移行事例 NECソフト PFシステム事業部 プロフェッショナル サポートグループ プロジェクトマネージャ 宇治郷 二郎 氏 発表資料(PDF:335キロバイト) |
| ●クロージング これからもCOBOL COBOLコンソーシアム会長 高木 渉 氏 発表資料(PDF:227キロバイト) |
| アンケート結果 |
また、次のグラフに示しますよう、ご参加いただいた皆様へのアンケート集計結果からも、COBOL、そしてCOBOLセミナーへの期待が高いものと確信させていただきました。次のセミナーについても、既に企画がスタートいたしました。内容と開催日が決定しだい皆様にお届けしたいと思います。
Q.今回のセミナー全体に関して、以下のものから当てはまるものを一つだけ選び○で囲んでください。
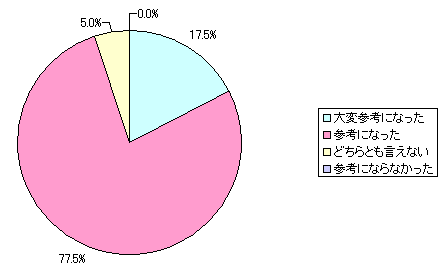
Q.今回のセミナーに関してのご意見・ご感想をお聞かせください。
- マイグレーションの成功例と失敗例は大変参考になった。
- 若い年齢層も増えて浸透していることが伺えた。
- 今後もより多くのCOBOLの現行の事態と将来を具体的に知りたい。
- 資料を後で詳細に読めるのがうれしい。
- 異なる業種での事例報告、面白く聞かせていただきました。
- 今後オープン化を進める上で大変参考になりました。

